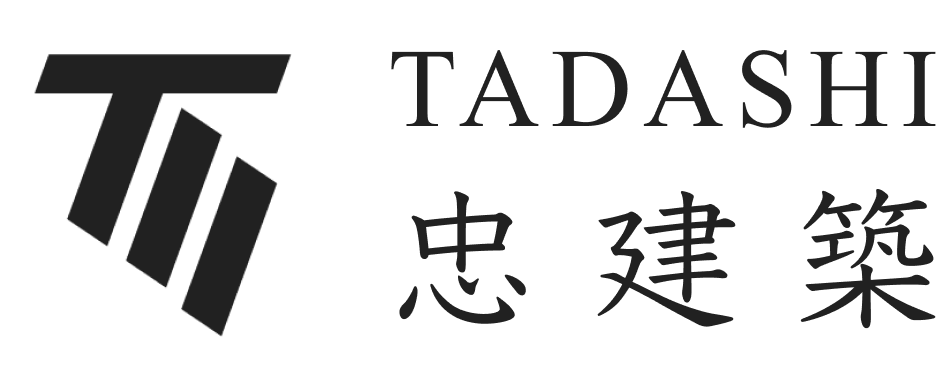こんにちは、忠建築の上山です。
今回は、いよいよ始まった宮大工修行の日々について書いてみたいと思います。
入舎したばかりの新人の仕事は、ご飯作りと掃除が中心でした。
「弟子になったらすぐに木を刻める」なんて、そんな甘いものではありません。
朝早く起きて、親方や先輩たちのご飯を用意する。
作業場や宿舎をきれいに掃除して、みんなが気持ちよく仕事に集中できる環境を整える。
これが、最初に与えられた大切な役割でした。
棟梁の小川三夫さんは、
「ご飯作りを見れば段取りの良さや人への思いやりがわかる。掃除を見ればその人の性格が出る」
そう話していました。
技術よりもまず、人としてのあり方を身につけること。
それを、毎日の生活を通して教えられたのです。
必死でご飯を作り、掃除をし、買い出しに走る毎日。
木に触れることもない裏方の仕事ばかりでしたが、不思議と嫌ではありませんでした。
「いつか自分も」と願いながら、目の前の仕事に一生懸命向き合っていました。
1年ほど経った頃、ようやく少しずつ木に触れさせてもらえるようになりました。
それはほんの短い時間でしたが、何よりも嬉しい瞬間でした。
けれど、そこからまた新たな壁に直面します。
修行3年目のある日。現場で任された仕事がどうしてもうまくいかず、思い悩んでいました。
「自分には向いていないんじゃないか」
そんな思いが頭をよぎり、気持ちが沈んでいた晩のことです。
晩ごはんのあと、量市さんが静かに声をかけてくれました。
「初めてやる仕事は、時間がかかっていい。
自分で『ここまでやったら完璧や』と思うところまでやって覚えなアカン。
8割くらいで『もうええか』と手を止めたら、お前の100%は本当は80%になってしまう。
そしたら、その仕事は必ず残ってしまうし、お寺さんにも申し訳ないやろ?」
その言葉は、胸にぐっと刺さりました。
手を抜いたつもりはなくても、自分で「ここまで」と妥協してしまえば、
それが自分の基準になってしまう。
そして、その積み重ねが、大切な建物にも、自分自身にも必ず返ってくる。
仕事はただ「できればいい」ではない。
誰かのために、そして自分のために、納得するまでとことんやりきる。
それが宮大工の仕事であり、職人としての心構えなのだと教えてもらいました。
それ以来、僕はどんな仕事でも「自分が本当に納得できるか」を大切にしてきました。
時間がかかっても、自分の目で見て、手で触れて、「これでいい」と思えるまでやりきる。
それが、今の忠建築の家づくりにも、しっかりと生きています。
次回は、地元に帰ることを決めた頃の話を書きたいと思います。
ここまで読んでくださって、ありがとうございました!