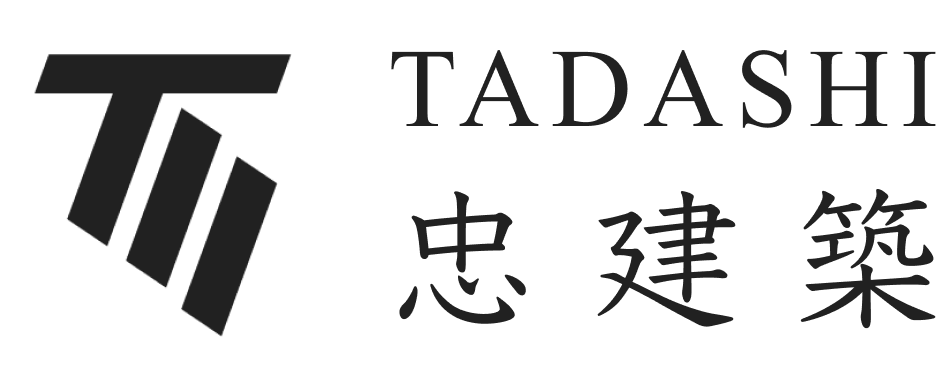こんにちは、忠建築の上山です。
今回は、修行を終えて地元に戻り、忠建築として仕事に取り組み始めた頃の話を書いてみたいと思います。
修行を終えて帰ってきたとき、まず感じたのは「ここからが本当の始まりだ」という緊張感でした。
ありがたいことに、父が長年かけて築いてきた基盤があり、いきなりゼロからの独立ではありませんでした。
けれど、それでも自分としては“挑戦の始まり”という気持ちが強かったです。
技術はある程度身につけてきたつもりでしたが、現場を任され、地域の中で信頼されるには、まだまだ足りないことばかりでした。
特に痛感したのは、建築の法律や設計に関する知識の不足です。
施工の技術は現場で叩き込まれてきましたが、建築基準法や構造、安全性、申請関係などはほとんど分からない状態でした。
「現場で動けるだけではダメだ」と思い、二級建築士の取得に向けて勉強を始めました。
父のように、技術だけでなく知識と責任を持って仕事に向き合える大工になりたい、そう思っていました。
また、どんな仕事にも対応できるよう、自分たちの作業場を建てました。
手刻みもできるし、プレカットにも対応できる。
「まずは地に足のついた体制を整えよう」という思いで、環境づくりにも力を入れました。
ただ、すぐに仕事があったわけではありません。
修行時代は社寺建築ばかりだったこともあり、住宅の現場では「住宅はやったことがないのか」とよく聞かれました。
地元の大工さんの中には、「お寺に比べたら住宅のほうが簡単だよ」と言う方もいました。
でも実際にやってみると、それが全く違うことを痛感しました。
寺は、檀家さんや住職さんなど関わる人が多く、誰か一人の思いにじかに触れる機会は少ないこともあります。
一方で住宅は、施主さんと直接やりとりをして、暮らしに寄り添うことが求められます。
一緒に悩み、一緒に形にしていく。だからこそ、完成したときの「ありがとう」の一言が、心にまっすぐ届きます。
お寺とはまた違った、やりがいと喜びがあることを実感しました。
社寺建築のような伝統構法とは違い、住宅の工法は日々進化しています。
断熱、耐震、省エネなど、学び続けることばかりです。
けれど、「この人の家を、自分が責任をもってつくる」という気持ちがあるから、自然と勉強にも力が入ります。
父の築いてきた忠建築という名前の重みを背負いながら、
そこに自分自身の学びや想いも重ねていく──
それが、今の僕の挑戦でもあります。
住宅も、社寺建築も、どちらも大切なお客様の「居場所」をつくる仕事です。
暮らしの安心を支える家も、地域や人の心を支えるお寺も、どちらにも丁寧さと真心が求められます。
これからも、宮大工として培った技術と心構えを生かして、
家づくりにも、社寺建築にも、誠実に向き合っていきたいと思っています。
次回からは、仕事の中で感じたエピソードなどを書いていきたいと思います。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました!